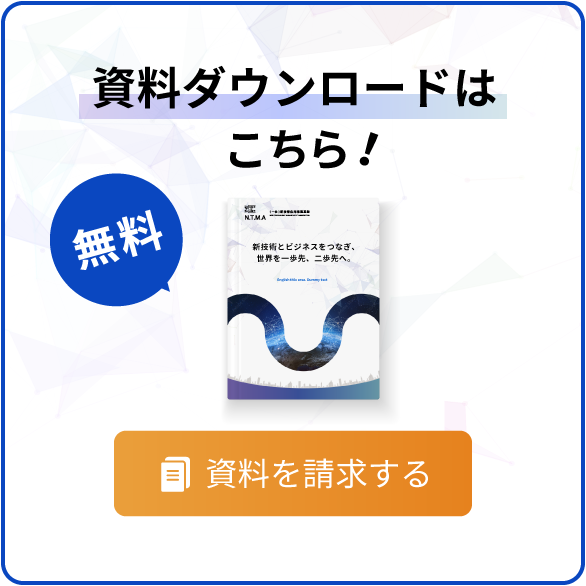研修会社の選び方 — “比較” ではなく “成果” から逆算するための5つの視点
「研修会社をどう選べば、自社の社員育成が確実に成果につながるのか --」
新人研修や階層別研修、リーダー育成やスペシャリスト育成など、企業の研修企画担当者にとって、毎年の大きな悩みになっています。Web上には「実践型研修」「即戦力化」「成果保証」といった情報があふれていますが、実際に導入すると期待通りの成果が出ず、時間や予算だけが消費されることも少なくありません。特に初めて研修会社を選ぶ担当者は、何を基準に判断すればよいか迷いがちです。
本記事では、そんな担当者のために、研修会社選びを単なる比較で終わらせず、成果から逆算するための視点を整理しました。
講師の実務経験や研修設計、現場連携、フォロー体制など、押さえておきたいポイントを明確に解説します。
目次
研修会社選びに迷う担当者が直面する現実
「どの研修会社を選べば成果につながるのか、正直わからない。」
これは、大手企業の人事・人材開発担当者や、技術系事業部の教育・企画担当者からよく聞く声です。
新人研修、階層別研修、特定のテーマ別研修 ―― いずれを実施するとしても、予算は数百万円から、期間や人数によっては1,000万円を超える規模。
間違った選定は、時間とコストの浪費につながるだけでなく、社員の成長や組織の競争力にも直結します。
しかし現実には、多くの担当者が「“どの研修会社が本当に自社に合うか” を評価する情報を持っていない」のです。
研修会社は数多存在し、パンフレットやウェブサイトの情報も似たようなものも多いのが現実。
「有名だから」「価格が安いから」という表面的な理由で選ぶと、期待する成果が得られないことが少なくありません。
研修会社選定で陥りがちな失敗には、実は共通のパターンがあると思います。
あなたの企業でも、下記のような選定の仕方をしてしまっていませんか?
「講師の肩書き」だけで判断する
博士号・MBA・人材育成の資格など、講師の肩書きに注目しがちですが、重要なのは「クライアント企業の課題の理解度、現場で成果を出した経験」です。
「研修の内容が豪華=成果」と思い込む
最新の研修教材や華やかなワークショップ形式に目が行きやすいですが、教材や手法だけでは行動変容は生まれません。
これだけでは、結局、現場に戻ったときに「実務で活かせない研修」になりがちです。
「価格最優先」で選ぶ
コストは重要ですが、成果を出す研修は投資として考えるべきです。
安価でも実務に直結しない研修は、むしろコスト高となります。
あなたの企業では、このような選び方をしてしまっていませんか?
もしも心当たりがあれば、ぜひ本コラムを参考にしてみてください。
成果を出す研修会社の共通点と、選定時に見るべき5つのポイント
では、成果を確実に出している企業が選ぶ研修会社には、どのような特徴があるのでしょうか。
私たちの経験で言えば、下記の5つの特徴があると考えています。これはそのまま、研修会社の選定時に見るべき視点でもあり、研修会社への提案依頼書(RFP)を作成する際にも、依頼先の選定の際にも確認しておくことをすすめています。
1. 講師が実務経験者であること
単なる教育専門家ではなく、企業でプロジェクトを推進した経験を持つ講師がいること。戦略と戦術、経営の想いと現場で起きている現実を理解した上で指導できることがポイントです。
研修の座学内容についてだけでなく、自社の業界や事業分野、企業文化について理解をしてくれているのか確認しましょう。
2. 研修設計が自社課題から逆算されていること
「これを学べば成果が出る」という逆算型設計がある研修会社は貴重です。
なんとなくそれらしい教科書について語るのではなく、「社員のパフォーマンス改善には、こういう理由で、こういう学びが必要だ」と語れる研修会社は強いと思います。
一般論で終わらず、「学び」を感じられるかを重視します。
3. 現場や経営層との連携力
研修を人事任せにせず、経営企画や事業部と協働して設計ができているでしょうか。
特に新卒研修では「人事部に設計から実行までお任せ」といった傾向もみられますが、研修を終えた新人を受け入れるのは事業部であり、その社員たちの成果に責任を持つのは経営です。
「成果を生む研修」とするには、現場や経営層を巻き込み、共通認識の下で進める提案力と企画力が求められます。
経営層からのレビューに耐え、部門横断で人材ニーズに応えている提案なのか確認しましょう。
4. 成果指標・フォローアップが明確
本来、「研修はやって終わり」ではなく、その後の行動変容などを追跡し、適切なフォローアップを重ねて成果につなげていくものです。しかしともすると、自社の担当者も研修会社も、当日の研修が終わると燃え尽きてしまい、その後のことはほったらかしになってしまうことが少なくありません。
開催日以降の拡大や、改善につなげる仕組みについて提案ができるかはポイントの1つです。
受講後アンケートのような形で参加者個人としての学びの有無を確認することはもちろんですが、事業のKPIと紐づけてフォローアップ体制を提案できるかは「成果を出す研修」にとって重要なことになります。
5. 長期的な育成視点を持つ
前項とも似ていますが、単発で終わらず、OJTや現場フォローも含めて設計されている研修は成果が継続します。
すべてを座学やワークショップで学ぶことは不可能ですし、その必要もありません。学びを現場に持ち帰り、そこでどんな行動を期待するのかまで見据えた研修設計となっているでしょうか。
初めて研修会社を選ぶ方へのアドバイス
ここで、はじめて研修会社を選定する方へ、ワンポイント・アドバイスを記載しておきます。
・ 研修会社の紹介資料だけで決めない
実際に講義を担当する講師と面談し、受講者に伝えられる内容のリアリティを確認しましょう。
・ 自社課題を具体的に伝え、それに対する提案を求める
漠然と「リーダー育成」ではなく、「現場で××の課題を解決できる人材を育てたい」と伝えましょう。
この具体的な課題に対して、どのような提案ができるかで研修内容に違いが生まれます。
・ 成果の定義を最初に決める
この研修によって達成すべきゴールを具体的に定め、そのゴールに向かう手段として妥当な内容か確認しましょう。
単なる満足度ではなく、行動変容や事業貢献を測定できる指標を設計することが望ましいと思います。
・ OJTや現場フォローも含めて検討
研修が終わって参加者が現場に戻った時、どう行動するかを想定しましょう。
その想定を望む方向に誘導するにはどのようなフォローアップが必要か、設計の際に考えておきましょう。
とくに注目すべきは、やはり「講師」であると思います。
いまや「オンライン学び放題」のような学習コンテンツは数多ありますが、そこでは公開されていない or オンラインでは体験できない学びや経験を提供するのに「講師」の存在は極めて重要です。
また、研修を学びや教育で終わらせず、「企業を成長させる取り組み」に進歩させるのも、研修内容を設計し、それを実践する講師の力に大きく依存します。
例えば次世代リーダーの育成研修であれば、講師は、
- 単に経営理論やマネジメント知識を教えるだけでは不十分
- 現場の抵抗をどう乗り越えたか、経営層とどう合意形成したか、といった具体的体験が必要
となるでしょう。
ちなみに、新技術応用推進基盤の講師は事業現場や研究戦略の最前線で成果を出した経験者となっています。このため、研修の内容は理論だけでなく、リアルな課題対応スキルまで伝えられます。
受講者からは、「研修というより実務プロジェクトの指導を受けている感覚」という声を聞いております。
まとめ — 研修会社は “選ぶ” のではなく “共に人と企業を育てる” パートナー
研修会社の選定は、単なる比較ではなく成果逆算の設計がポイントです。
実務経験豊富な講師と共に、経営・現場・人材育成をつなぐ仕組みを作れる会社こそ、真のパートナーと言えます。
もし貴社が、
「研修会社選びで失敗したくない」
「実務で成果を出せる研修を導入したい」
と考えているなら、ぜひ一般社団法人 新技術応用推進基盤にご相談ください。
経験豊富な講師陣と、成果に直結する研修設計で、貴社の人材育成を次のレベルへ導くお手伝いをさせていただきます。
新技術応用推進基盤の法人研修について
※本記事の一部は、生成AIを活用して作成しました。内容は社内で確認・編集を行っていますが、表現や情報に誤りが含まれる場合があります。参考情報としてご利用ください。