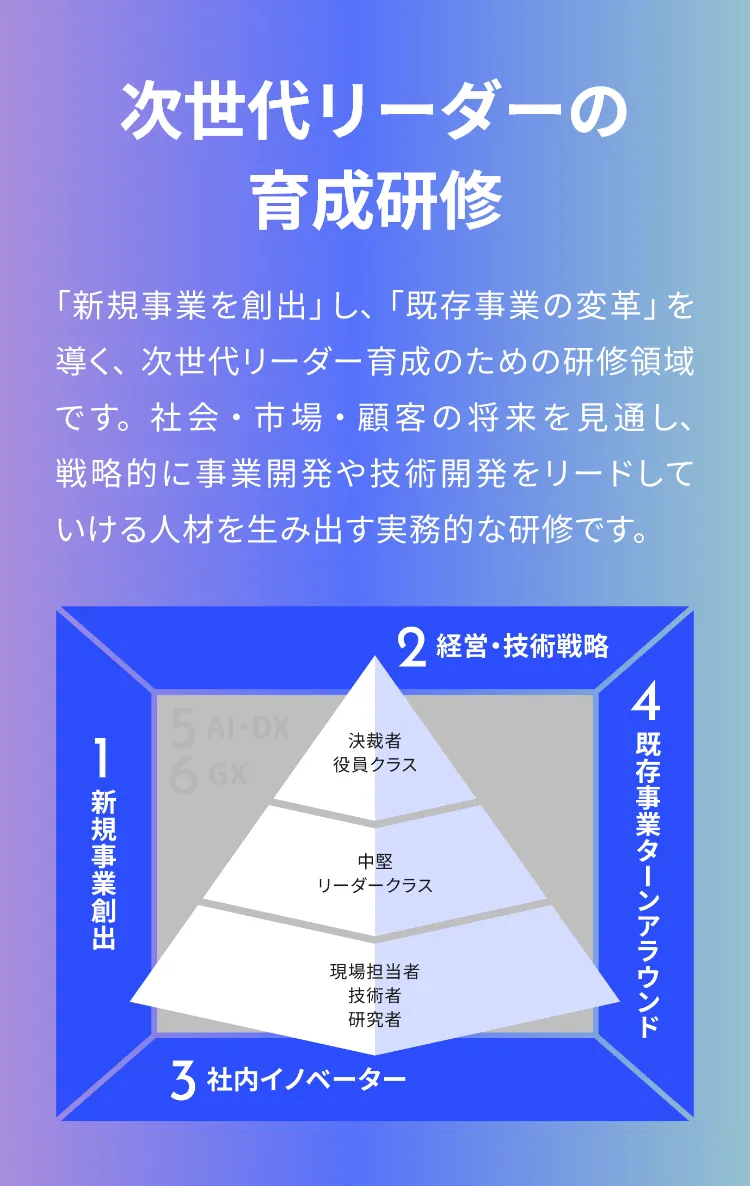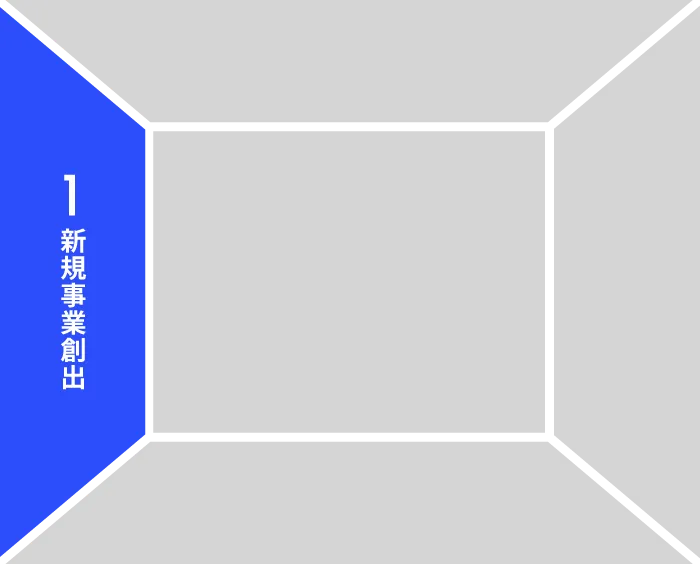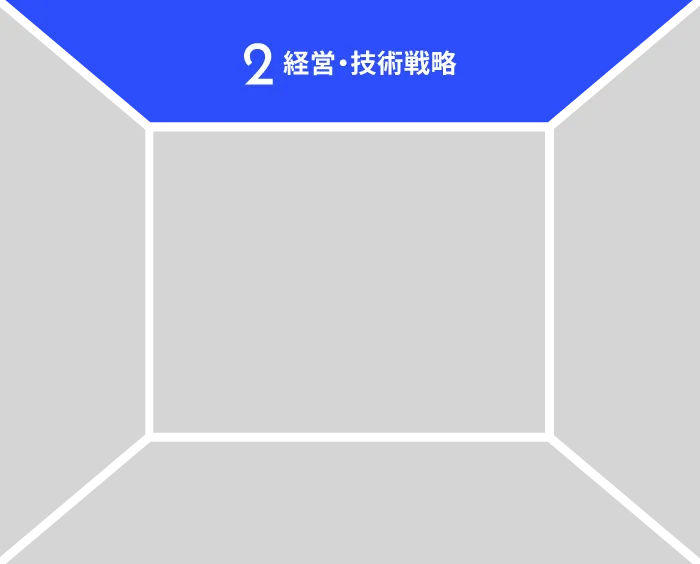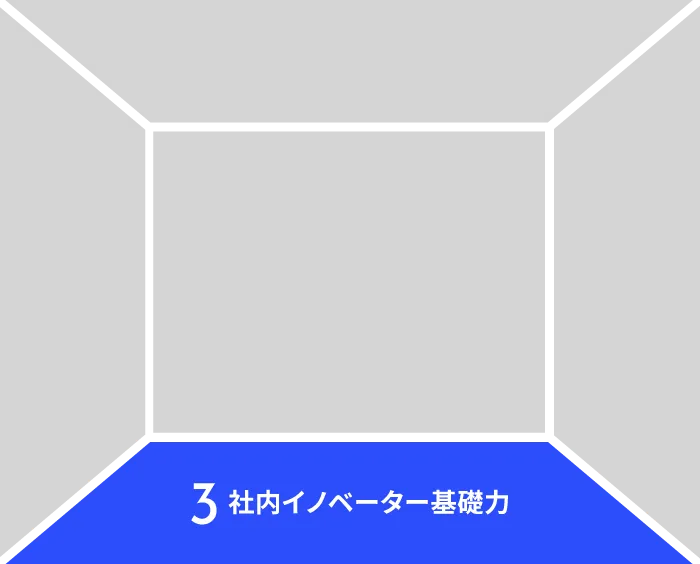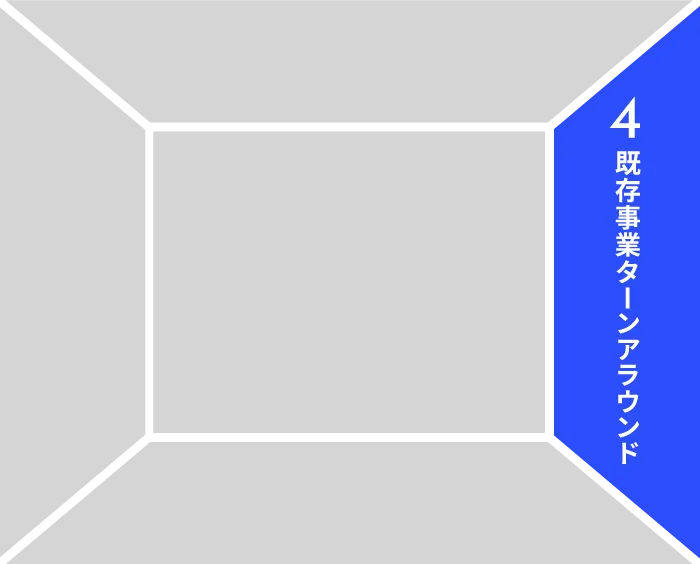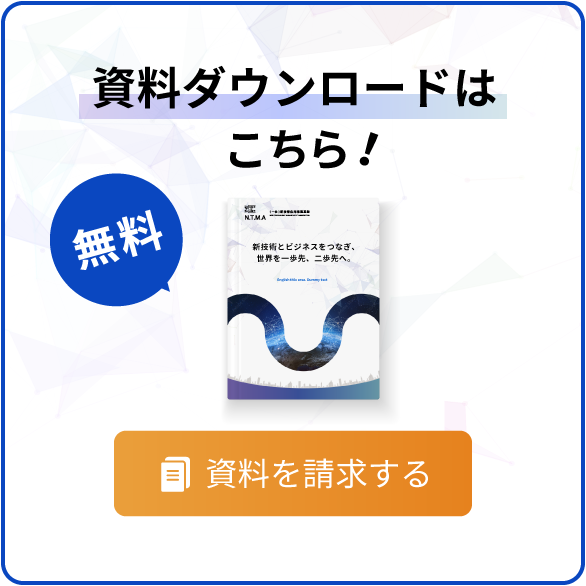日系企業の研究開発の「質」の低さは各種統計*でも指摘される。
・R&D投資に対する5年後の付加価値は、1990年と比較し80倍→30倍と大きく下落
・10年前のR&Dと技術的近似性が高く、新規分野を開拓できていない
実感値としても「次世代の収益の柱」となりえる事業のネタは不足している。
新規分野に挑戦し成果を出せる人材、そうした人材及びテーマが継続的に生み出される仕組み/組織の構築なくしては、多くの企業で継続的発展に黄色信号がともりかねない。
* 経済産業省『イノベーション小委員会中間とりまとめ』(令和6年6月)