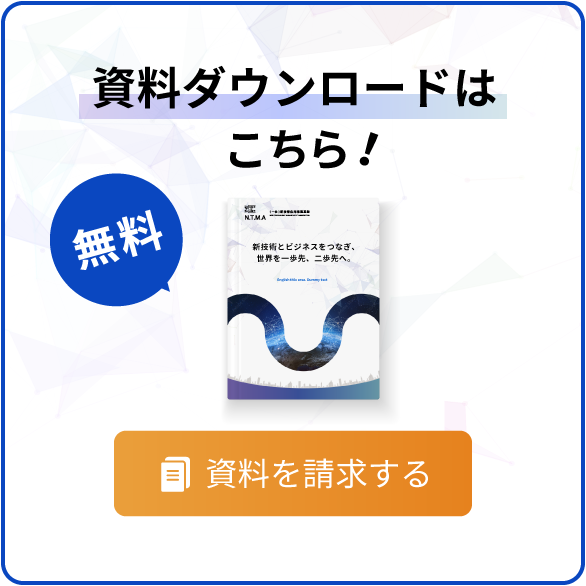組織に「深み」を与える専門人材育成 — 成果に直結するテーマ別研修のつくり方
目次
専門人材育成は、技術教育だけにとどまらない
「技術者はそれなりにいるはずだが、成果につながらない。」
これは近年、多くの製造業・研究開発部門・技術企画部の方々が抱えている共通の課題です。
かつての日本企業では、工学系技術の深堀りを続ければある程度それが競争力として機能しました。
しかし、近年は社会課題の複雑化、技術の融合化、AIやデータ活用の進展により、「技術的専門性・経営的専門性・それらを土台に競争ストーリーを語れる創造性」の3本柱が求められています。
つまり、「技術を“知っている人”から、技術で“価値を創り出せる人”へ」 - この転換をどう実現するかが、企業の未来を左右するようになっていると言えるでしょう。
こうした転換に対応するにあたり、従来のOJTを中心とした専門教育や年次ごとの階層別研修は、十分に用を果たせなくなってきています。
部署に受け継がれてきた専門性だけでは視野は広がりませんし、ゼネラリスト的な階層別研修だけでは内容が一般的に過ぎるからです。
そこで今、多くの企業が導入を検討しているのが「テーマ別研修」です。
テーマ別研修とは、特定の経営課題にフォーカスし、その分野で組織の中核を担う人材を集中的に育てる仕組みです。例えば、
- 新規事業創出研修(研究戦略・技術企画スキル)
- DX推進人材研修(データ活用・AI応用・業務変革)
- 知的財産戦略研修(技術×事業視点の特許活用)
- サステナビリティ対応研修(環境技術と経営の融合)
など、単なるスキル教育ではなく、経営課題を解く専門人材育成に主眼を置くものになります。
私たち、新技術応用推進基盤が得意としているのはまさにこうした専門人材の育成研修です。
テーマ別研修で成果を出すには?
しかし、 「テーマ別研修を企画したものの、どうも成果が見えにくい」 - そんな声も少なくありません。
その原因として、当団体がよく聞く声が下記の3つです。
1. テーマが「時流先行型」になっている
DXやAIなど、トレンドキーワードに引きずられ、「自社が本当に克服すべき課題」と結びついていないケース。
トレンドをおさえることは重要ですが、流行にのっているだけで目的不在な状態では本末転倒です。研修が実践に結びつかず、なんとなく勉強しただけとなってしまいます。
2. 座学に終始しすぎる
座学で新たな知識や学びを得ることは重要ですが、それ以上に「実際の業務で試す」「その結果から改善を考える」というプロセスをまわしていく経験が深い学びへとつながります。座学だけでは成果が出ないのはもちろん、個人から組織へ学びが波及していきません。
3. 部門横断の連携を欠いている
テーマが専門的になるほど、実は部門間連携が鍵になります。しかし、研修企画を各部門がバラバラに進めてしまい、成果が全社に波及しないという問題が起こりがちです。
テーマ別研修を企画する方へのポイント
テーマ別研修は一見すると専門的で難しそうに感じますが、次の3つを押さえると設計の精度を上げていくことができます。
①「目的」を“経営上の課題”で言語化する
「AIを学ばせたい」ではなく、「AIを活用して生産性を高めたい」。「知財教育をする」ではなく、「知財を事業の武器にしたい」。 —研修の目的を“経営目線で翻訳”することが、成否を分けます。
②「現場テーマ」を取り込む
経営課題と現場課題の両方を扱うことで、「学びを自分ごと化」できます。
新技術応用推進基盤では、受講者自身が自社テーマを持ち込み、講師がプロジェクト形式で指導するケースが多くあります。
③「経営レビュー」で締めくくる
研修の成果を経営層に直接プレゼンさせることで、参加者の意識が一気に変わります。
また、経営側も研修を“経営投資”として捉えるきっかけになります。
【ケース】経営戦略と技術戦略 研修の場合
例えば、ある製造業の技術開発部門を考えてみましょう。
A社では、研究開発部門における技術テーマ選定の偏りが課題でした。
各部門が独自判断でテーマを進めており、極端な話、個人の好き嫌いで研究テーマを決めているような状況で、そこには技術戦略も技術ポートフォリオもない状態でした。
社長を始めとした経営陣もこうしたR&Dの姿勢を問題視していましたが、A社の製品は技術的に複雑で、経営陣といえど知らないことも多々あります。この事実がある種の”弱み”となって、なかなか問題を指摘しづらくなっていたのです。
また外部の経営コンサルタントも、この不健全な状態をたびたび指摘していましたが、人が変わらなければ組織の行動も変わるはずがありません。なんとなく問題だろうとみな把握しつつ、状況は改善されないまま続いていきました。
そんな状況では、だんだんと経営方針と研究テーマの整合性がずれていくのは当然です。結果的に「研究成果が事業化に結びつかない」、「中央研究所が事業に貢献していない」という問題が顕在化していきました。
ここにきて、若手を始め研究所の内部でも危機感を持つ社員が現れましたが、社風や慣習はそう簡単に変わるものではありません。年々落ちていく収益性を横目に、「誰もが危機感をもっているのに、行動できない」状態となっていたのです。
会社員として、似たような状況を経験している方も多いのではないでしょうか。
こうした状況では、トップダウンの指針や経営コンサルタントからの提言だけでは力不足です。現場を巻き込み、人が成長して行動する必要があるからです。そんな時に、テーマ別研修を使った行動変容が役に立ちます。
「経営戦略と技術戦略の策定研修」
- 経営戦略の方向性を確認し、進むべき技術ドメインを定義(経営戦略の技術戦略への落とし込み)
- 現状の各部門の研究テーマを可視化・分類(現状の正しい把握)
- 10年後の市場変化を仮定し、必要な技術要素を逆算(強みを持てる領域の探索)
- 部門横断で技術ロードマップを構築(具体的な計画の策定)
- 3か年計画の策定(足元の実施事項整理とKPIの設定)
このプロセスを「研修」という形で実施することで、押し付けでなく自ら動くことを促します。
「研修」という場であることで、現場メンバーは失敗を恐れたり、社内政治に遠慮したりする必要性が薄くなり、本音に近い言葉で取り組むことができるのです。
「研修」ではありますが、これが単なる社員教育ではなく、組織の変革を促すための起爆剤であることがわかるかと思います。
教育という側面だけにフォーカスしても、知識伝達ではなく、社員1人1人の成長そのものにつながる経験となるのです。
A社では、研修後に「自部門テーマの見直し」が実施され、経営会議でも技術戦略が正式に採用されたようです。
これにより、「戦略的な研究開発」の第一歩を踏み出すことができました。
「教育」を超え、「知の共有基盤」へ
テーマ別研修の本質は、「専門知識を教えること」ではありません。
それは、組織の中に“共通の理解と知の文脈”を築くことです。
一人の専門家が持つ知見が、組織全体に伝播し、やがて新たな価値を生み出すサイクルが生まれる。
こうした組織に行動変容を起こすきっかけの提供こそ、テーマ別研修の本来の目的なのです。
研修を「知の共有基盤」と位置づけ、人材育成を企業変革の持続的エンジンとして考えていただければ幸いです。
■ 新技術応用推進基盤が提供する実践型テーマ別研修
なお、テーマ別研修を成功させるには、扱うテーマに精通し、かつ経営の文脈で語れる講師が不可欠です。
しかし、多くの研修会社では「教育分野出身の講師」が中心で、専門性の深い技術テーマや経営戦略テーマには対応しきれないことがあります。
新技術応用推進基盤では、現役の経営コンサルタントや技術戦略アドバイザーが講師を務めます。
当団体のテーマ別研修プログラムは、次の特徴を持っています。「学んで終わり」ではなく、「実行して変わる」ための仕組み構築を意識しています。
- 技術系・研究開発系企業に特化した実践設計
- 経営課題と現場課題を接続する「課題持込み型」構成
- 実務経験豊富なコンサルタント講師によるファシリテーション
- 経営層レビューまでを含む成果志向のプログラム設計
- 研修後のプロジェクト化支援(フォローアップあり)
おわりに —専門人材を「戦略人材」へ
これからの企業競争では、「技術を持つ」ことだけではなく、「持っている技術で、成果(儲け)を生む戦略を描けるか」がいっそう大切になってきます。
テーマ別研修は、その第一歩を支える仕組みとなりえるでしょう。
もし貴社が、
「専門人材を経営に貢献できる人材に育てたい」
「研修を通じて知の連携を生み出したい」とお考えでしたら、ぜひご相談ください。
一般社団法人 新技術応用推進基盤は、「現場を知る講師」と「実践設計力」で、貴社のテーマ別人材育成を確実に成果へ導くお手伝いをさせていただきます。
※本記事の一部は、生成AIを活用して作成しました。内容は社内で確認・編集を行っていますが、表現や情報に誤りが含まれる場合があります。参考情報としてご利用ください。